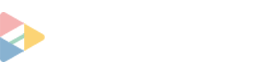中井智弥箏・三味線レッスンキャンプ
90.1ランク上の8つの技術
- 全て見放題 (月額)
何を弾いてもベターっと平面的な演奏から表情豊かな演奏になりたい貴方のための動画が完成! プロ仕様のなかでもかなり高度な技術です。 もちろん今までの動画のあちこちで申し上げている事ではありますが、敢えて習得しにくい技術だけ取り上げてみました。 ❶手首の位置と向こう指の曲げ伸ばし ❷腕と指の自然な連動 ❸トテトテ手首のスナップ ❹意外と指が動かせていない掻ぎ爪 ❺1フレーズごとの脱力 ❻音圧の上げ方 ❼Pizz.の準備とどこまであげるか ❽フレーズの速さとと動かす距離 じっくり一つ一つ取り上げて考えなくてもこの技術がつかえるようになれば、貴方はプロ!?
89.薬指の支え方
- 全て見放題 (月額)
指導時に見逃しがちな薬指。また練習の時もあまり意識がいかない薬指。 支え方によって向こう指の関節可動域がかわっるので親指の動きも変わってきます。すなわち音色に大きな差がうまれます。 薬指の支え方に意識が回ると大きな技術向上につながり、ご自分の手を箏弾きの手として成長させる大きな一歩となります。 この機会に今一度確認してみてください。手のアーチが深くなり握る力を利用して演奏できるようになるとおもいます。 また、中指を使う時の薬指の位置関係も解説しています。大事なことは空中で薬指と中指との位置関係です。一緒に動かしすぎないで基本の弾き方に立ち帰り、中指を使う時は薬指の位置を糸に中指より先に着く位置関係にしましょう。
88.春の曲後歌
- 全て見放題 (月額)
春の曲いよいよ後歌の解説です。散らしをおえて、後歌に入るテンポ感歌詞から手と歌のかけ引きなど、もろもろ解説しています。
87.春の曲チラシ
- 全て見放題 (月額)
春の曲の散らし、手事の雰囲気を散らして後歌に入る場面ですが、後歌は桜が散る春の終わりを歌っています。桜を散らす少し暖かな春風をイメージして演奏してみてはいかがでしょうか?節の長さが印象的で、それぞれの節の拍数はまばらです。春風はまさに気分屋的なところがうまく表現できるといいですね。
86.春の曲 本手事
- 全て見放題 (月額)
本手事の解説になります。鶯の谷渡りなど小気味よく聴かせるためのコツをお伝えしています。春闌の様子を描けるように練習してみてください。
85.春の曲 枕
- 全て見放題 (月額)
枕の部分になります。ノリ方、演奏方を解説しています。アッチェレランドではなく、節を一つ一つのブロックに考え、階段状にのっていきます。
84.春の曲前歌その2
- 全て見放題 (月額)
春の曲前歌の後半になります。曲の演奏のコツの解説になりますが、歌い方のちょっとしたアドバイス、手の弾き方等をお伝えしています。
83.春の曲 前弾き・前歌その1
- 全て見放題 (月額)
古今物の花形!!春の曲の解説です。 べたーーーっとインテンポで弾きがちな曲ですが、節にメリハリをつけて歌と手とのかけ引きを楽しみましょう!素敵な作品になります。 春の中でも季節のうつろいを感じて弾けるといい仕上がりになると思います。 歌が私には高いので一音下げて歌っています。
82.ノーミスの瀬音 その2.3
- 全て見放題 (月額)
ノーミスで弾くコツを説いた動画になります。 説明箇所は瀬音の中間部からラストにかけて。 正しい演奏法で反復練習を積まないと必ず本番では失敗する恐ろしい曲です。さりとて安全運転の速度ではうまく曲想を表現しきれません。 瀬音を弾き切るにはやはり正しい手の使い方で繰り返し練習し、ご自身の手を箏の演奏家の手に育て上げることが重要になります。 一つ一つの技術が物を言うので、できない箇所は今一度昔の動画にもどり、テクニックを確実にしてください。それがないと、どんなに練習しても晴れやかな気持ちで曲は仕上がらないと思います。 華やかな一面地味な練習が物を言う曲です!頑張ってください!!
81.ノーミスの瀬音 その1
- 全て見放題 (月額)
一発勝負が続き、難所だらけの瀬音。 曲想だけでなく、技術も荒波に揉まれがち。。。😢 という憧れの曲の成功率をあげるべく、 弾き方のコツと練習の仕方を伝授します。 瀬音初心者も瀬音上級者も見てほしい珠玉の動画です。
80.鮮やかに弾こう!春の海 その2
- 全て見放題 (月額)
春の海中間部の演奏のコツをお伝えしています。 リズムにしっかりハマった、キレキレの中間部の演奏は難しいですよね。 でもちょっとしたことで、うまくできるんです! 是非この機会に春の海、一皮剥いてみてくださいw
79.鮮やかに弾こう!春の海 その1
- 全て見放題 (月額)
お正月の定番、春の海。 箏の代表曲、春の海。 憧れや曲だったり、弾き慣れた曲でもあるとおもいますが、みなさんどのような情景を描いていますか?かなり具体的に描くと、音楽が色鮮やかに聴き手に伝わります。 動画では宮城曲ならではの音選びのコツや、春の海の情景が描ける弾き方を解説しています。 どうぞ参考にしてみてください!
1,さりとてテンテンテン 基礎中の基礎編
- 無料
箏のワンポイントレッスン動画。ちょっとした工夫で上手く弾けるテクニックやプロの技を伝授します。 まずは箏演奏の基本中の基本であるテンテンテン。親指で弾くテクニックを紹介します。 弾き方の基本、そして弾くための準備のタイミングについてお話ししています。 剃り指の方は手を狭めに構え、棒指の方は自然に置いた時の手の幅で演奏していきましょう! 爪は弦につけ、脱力に心がけてください。人差しから薬指が一直線上になったり、中指だけ下の弦にいっても大丈夫です。とにかく丸く手をおいてみましょう。 速いパッセージが弾けない人、音が充実しない人、どの曲を弾いても同じ仕上がりになる人。是非動画を参考にし、テクニックの向上にお役立てください。 もちろん流派や先生により考え方や趣向は異なりますが、私自身が師匠からまた様々な経験から習得したものになります。なるべくどの流派でも使える癖のないテクニックをご紹介したいとおもいます。 癖をなくす事は上達につながり、様々な曲に対応できます。音色を作る技術の引き出しを広げて音楽として箏曲を楽しんでいきましょう!
78.救いきれないスクイ爪
- 全て見放題 (月額)
今までなんとなく?出来ていたかも知れないスクイ爪、高速のスクイ爪ができない!と嘆いていた貴方。 中井智弥が贈る救いのスクイ爪レッスン! スクイ爪の強弱の付け方もさまざめな方法があり、組み合わせることでさらにやりやすくなります。また、高速スクイ爪もちょっとしたコツでミスりにくくできます。
77.恥晒し風手事低音❸
- 全て見放題 (月額)
さらし風手事低音の練習番号 ④⑤⑦の解説です。
76.恥晒し風手事低音❷
- 全て見放題 (月額)
さらし風手事低音の練習番号②の解説になります。
75.恥晒し風手事低音❶
- 全て見放題 (月額)
さらし風手事低音の前弾きと練習番号①②の解説です。
74.ビブラートのかけ方
- 全て見放題 (月額)
ご質問があったビブラートのかけ方です。特にやり方はないのですが、私の場合のやり方、ビブラートのあり方、かけると良くなる場所の説明などしています。自分の感覚で現代曲にお使いください!
73.脱・恥さらし風手事❸
- 全て見放題 (月額)
さらし風手事 高調子最終回④⑤⑦の解説です。 音の立ち上がりを意識した合わせ爪、軽く弾くコツ、表間を弾くときと裏間を軽く弾く時の違いを出すコツなど解説しています。 イキイキとしつつも涼しげなさらし風手事をこれで目指してください!
72.脱・恥さらし風手事❷
- 全て見放題 (月額)
さらし風手事の中間部の解説になります。 早引きのさまざまなコツ、力の抜きどころのコツ等、楽曲から具体的に解説しています。 お手本動画もあります。
71.脱・恥さらし風手事❶
- 全て見放題 (月額)
さらし風手事は手物の基礎強化に適した楽曲です。しっかり暗譜して、いつでも弾けるようにしておくと、基礎的なフレーズの動きを長い時間かけて手を鍛えられます。 うっかり古典の時にミスすることが少なくなると思います。 この機会に正しい弾き方で、キレキレのさらし風手事を弾きませんか?
70.低調子のコツ 八千代獅子手事編
- 全て見放題 (月額)
低調子は四の押手になかなか行けない、弾きにくい、曲にならないなど色々お困りのことがあると思います。実際高調子を弾くことに慣れていると低調子が弾きにくく思われるのも納得です。 低調子ならではのちょっとした弾き方がありますので、この機会に身につけて面白い楽曲にチャレンジしてみてください! 座る位置、脚の位置、重心のかけ方、弾く位置、爪の面積、腕の角度など動画でコツをお伝えしています。
69.脱力シリーズ つち人形
- 全て見放題 (月額)
つち人形を使って古典の手の脱力の仕方の解説をしています。 弦から離れない弾き方もありますが、弦からわざと手を離してしっかり動きのある、空気感や余韻のある演奏に是非トライしてみてください。
68.脱力シリーズ 三段の調(初段)
- 全て見放題 (月額)
三段の調は初歩の曲の中でも人気で映える曲ですね!古典の手が特にたくさん使われている初段を使って脱力のための弾き方を解説しています。
67.脱力シリーズ 飛躍
- 全て見放題 (月額)
脱力するべきところ、仕方を細かく解説しています。節の入口、節尻をつかってうまく脱力して楽に演奏していきましょう。フレーズ感にも繋がる根本的な練習です。 細かなテクニックはこれまでにもやっていますが、曲中や曲を通してどう脱力するかをこれからシリーズで取り上げます。 弾きやすい曲や初歩的に譜面を見なくても弾けるくらいの曲からこの練習をすることをお勧めします! 今回は飛躍を使って解析しています。
66.末の契り後歌編 歌唱のコツ
- 全て見放題 (月額)
後歌の冒頭のクライマックスを歌い切るコツを主に解説しています。 前歌を歌い、手事を終え集中力がきれそうなときにクライマックスがやってきます。そんな時の声の響きのポジションをどう保つかなどお話ししています。
65.末の契り手事編 弾き方のコツ
- 全て見放題 (月額)
末の契りの手事の弾き方ですが、低調子でベターっと弾きがちです。三味線をたてながら、箏もカッコよくうるさくならないコツを解説しています。 とにかく一節がどこからどこまでで、節頭・節尻の処理。パリッと弾く節の見分け方などとても大切な話をしています。 他の曲にも通じることなので是非末の契りで習得しましょう!
64.末の契り前歌編 休符の取り方
- 全て見放題 (月額)
前歌のゆっくりなところはベターーーっとなりがち。しかも低調子だとなおさら。 そんな時は手だけでもメリハリのあるものにしたいですね。宮城譜だと半拍の休符の△をどう感じるか、どう準備するかで裏拍の立てるべき音が印象的に演奏できます。そこから、ベターっと弾かない手の糸口が見つかるかもしれませんね! それから、前歌の前半の歌い方のコツなどお話ししています。
63.末の契り前歌編 白波問題
- 全て見放題 (月額)
白波の という歌詞の歌い方のコツの動画になります。同時に前歌をどう歌うと全曲通してべたーっとならないかというお話もしています。 ど頭の 白波の 歌い方で前歌を支配してさはまいます。 気負いせず歌うけど、何もやっていないようですごくいろんなテクニックが織り込まれている、という着地点が理想です。
62.さりとてテンテンテン マスタークラス
- 全て見放題 (月額)
第1回目の「さりとてテンテンテン」 をさらに筋肉や関節の使い方、練習方法を解説。 基本中の基本をこのタイミングでもう一度確認、 練習してみてください! 曲を使うときはゆったりとした手数が少ない曲を選ぶと いいですね。 弾く前に親指を上げるわけでなく 実は向こう指が上がって親指が上がっているところを 是非ご覧ください。 大切なのは向こう指の動きです。
ショップ管理者にチップを送って応援しよう!
チップを送る