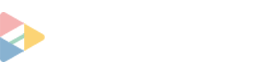地域活動とリハビリの接点-介護予防事業における軽度者支援から学ぶ-
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
介護予防の現場では、要支援者や軽度者に対するリハビリの関わり方が大きく変化しています。 個別訓練だけでは生活機能の維持・向上につながりにくく、地域活動や住民主体の取り組みとどのようにつながるかが、介護予防の成果を左右する時代になっています。 本セミナーでは、介護予防事業における軽度者支援をテーマに、地域活動とリハビリテーションが交わるポイントを整理します。 通いの場や地域サロン、住民主体の活動に対して、リハビリ職がどのような立場で関わるべきか、専門性をどこまで発揮するのかについて、実践的な視点で解説します。 軽度者支援では、「治す」ことよりも「続けられる仕組み」をつくることが重要です。 専門職が前に出すぎても住民の主体性は育たず、関与が弱すぎても効果や安全性を担保できません。 本セミナーでは、その適切な距離感や関わり方を具体的に学びます。 これから地域包括ケアの中で役割が広がるリハビリ職にとって、地域活動との接点を理解することは不可欠です。 地域での介護予防に関わりたい方、軽度者支援に課題を感じている方に、ぜひご参加いただきたい内容です。 講師 浅田健吾先生 株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩 在宅リハビリテーション&ケアスクール 講師 平成21年に関西医療技術専門学校を卒業し、作業療法士の免許取得する。 回復期・維持期の病院勤務を経て、令和元年より訪問看護ステーション彩での勤務を開始する。 在宅におけるリハビリテーション業務に従事しながら、学会発表や同職種連携についての研究等も積極的に行っている。 大阪府作業療法士会理事を務めている。 また、平成30年からは大阪府某市において自立支援型地域ケア会議や短期集中介護予防サービスでも活動している。
基礎から学ぶ膝関節の可動域制限に対するアプローチ
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
膝関節の可動域制限は、歩行や立ち上がりといった日常生活に直結し、患者の自立度や生活の質に大きな影響を与えます。 そのため、正しい評価と適切なアプローチを理解しておくことは臨床現場で欠かせません。 本動画では、膝関節の解剖や運動学的特徴を整理し、なぜ制限が生じるのかを明確にした上で、筋や靭帯、関節包、軟部組織といった多角的な観点からの評価方法を解説しています。 加えて、得られた評価結果をもとに治療戦略を立てる流れを具体的に示し、実際の臨床で活かしやすい形にまとめています。 ストレッチや単純な訓練にとどまらず、原因を特定して根本的にアプローチする姿勢を学べるのが特徴です。 オンデマンド配信なので時間や場所にとらわれず、繰り返し視聴することで理解を深められます。 基礎から学び直したい方や、自身の臨床力を高めたい方におすすめの内容です。 講師 川﨑 友祐希先生 医療法人寿山会 法人リハビリテーション部 理学療法士 認定理学療法士(運動器・徒手) 専門理学療法士(運動器)
科学的根拠に基づく手の徒手検査法
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
本動画では「科学的根拠に基づく手の徒手検査法」をわかりやすく解説しています。 従来の経験や感覚に頼った検査ではなく、エビデンスを踏まえた評価手法を学ぶことで、臨床現場での信頼性と再現性を高めることができます。 内容のポイント 1)各徒手検査法の科学的根拠を整理 2)検査の実施手順を動画で丁寧に解説 3)臨床で活用できる評価の視点を習得 日常臨床の「なぜこの検査を行うのか」を明確にし、患者さんへの説明にも自信を持てるようになります。 いつでも視聴できるオンデマンド形式ですので、繰り返し学習しながら知識と技術を定着させていただけます。 講師 竹中孝博先生 平成医療短期大学 准教授 作業療法士 博士(保健学) 専門分野 運動器作業療法 神経生理学 慢性期片麻痺患者に対する運動イメージ介入
大腿骨近位部骨折リハビリの基本と実施~評価・運動療法・ADL支援~
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
大腿骨近位部骨折は高齢者に多く、再転倒・ADL低下・在宅復帰困難など多くの課題を抱える重要な疾患です。 本セミナーでは「評価」「運動療法」「ADL支援」の3つの観点から、現場で役立つ実践的アプローチをわかりやすく解説します。 筋力やバランス能力だけでなく、疼痛、恐怖心、環境要因にも配慮した介入戦略を学べます。 特に、術後早期から在宅生活を見据えた支援の流れ、他職種との連携のポイントも紹介します。 臨床経験が浅い方にも理解しやすい構成で、明日からの実践にすぐ活かせる内容です。 回復期・維持期のリハビリに携わるすべての理学療法士・作業療法士におすすめです。 動画配信でじっくり学び、根拠あるケアの引き出しを増やしましょう。 講師 堀口怜志氏 医療法人寿山会 法人リハビリテーション部 リハビリ特化型デイサービス リファイン 理学療法士 認定理学療法士[運動器・脳血管・代謝・物理療法] 3学会合同呼吸療法認定士
生活期リハビリの価値と役割~自立支援と生活再建の実践ポイント~
本動画では、生活期リハビリテーションにおける本質的な価値と役割について、実践現場で活かせる視点から解説しています。 単なる身体機能の回復にとどまらず、「自立支援」や「生活再建」という視点を重視し、利用者の生活背景や目標に応じたリハビリテーションの在り方を具体的に紹介します。 地域包括ケアが進む中、生活期リハに携わる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士に求められる視点やチーム連携の重要性、そして介護予防や在宅支援との関係性についても言及しています。 すぐに臨床に活かせる実践的な知識を得られる内容となっています。 講師 小池 隆二先生 株式会社OneMoreShip 代表取締役 在宅リハビリテーション&ケアスクール 講師 理学療法士 株式会社OneMoreShip 代表取締役 医療法人OneMoreShip 理事
心配運動負荷試験(CPX)の基礎と活用
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
心配運動負荷試験(CPX)は、循環器・呼吸器リハビリや運動療法の現場で注目される評価法です。 本動画では、CPXの基本的な原理から臨床活用までをわかりやすく解説しています。 VO2peak、ATなどの指標の意味や測定のポイントを丁寧に説明し、実際の評価データの読み取り方や注意点も学べます。 初心者の方でも理解しやすい構成となっており、リハビリテーション、心不全管理、介護予防、運動処方など幅広い領域で役立つ内容です。 忙しい臨床の合間に繰り返し視聴できるオンデマンド形式ですので、確実に知識を定着させることができます。 ぜひこの機会にCPXの活用スキルを高めてみませんか? 講師 井上拓也先生 医療法人 白岩内科医院 理学療法士 高度専門士 3学会合同呼吸療法認定士 心臓リハビリテーション指導士 認定理学療法士(循環) サルコペニア・フレイル指導士 心電図検定1級 理学療法士免許取得後、急性期から訪問リハビリまで幅広く臨床経験を積む中で、内部障害リハビリの重要性を実感。専門資格を取得し、リスク管理と運動負荷量の最適化を重視した安全かつ効果的な運動療法を実践している。
基礎から学ぶ運動学習ー臨床で生かせる運動学習を学ぶー
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
「その練習、本当に効果がある?」 患者の動きが変わらない・・ そんな壁に直面していませんか? 臨床現場では、「正しい動き」を伝えるだけでは成果に結びつかないこともあります。 本セミナーでは、運動学習の理論をわかりやすく解説し、臨床の現場で「動きを引き出す」視点とアプローチを学びます。 このような方におすすめ! 運動学習の基本を改めて整理したい方 脳卒中や神経疾患患者のリハビリに関わる方 リハビリ効果が出にくい患者へのアプローチに悩んでいる方 講師 福本 悠樹先生 理学療法士 Ph.D. 関西医療大学 保健医療学部 理学療法学科 講師 関西医療大学大学院 講師 関西医療大学附属診療所 リハビリテーション科 認定理学療法士(神経筋障害 / 脳卒中)
リハビリ職種が知っておきたい方向転換動作と特徴と転倒予防の基礎知識
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
リハビリ職種は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく生きがいを持ち、役割を果たしながら生活できるよう支援する重要な役割を担っています。 その中でも特に注意すべきは「転倒」です。転倒は骨折などの身体的な後遺症だけでなく、心理的な萎縮や活動量の低下を招き、生活レベルを著しく低下させるリスクがあります。 だからこそ、転倒予防はセラピストにとって欠かせない責務と言えるでしょう。 今回の動画では、転倒リスク要因の整理、歩行時の方向転換動作の注意点、転倒とバランス機能評価のポイント、さらに体幹機能に着目した転倒予防の考え方についてわかりやすく解説しています。 日々の臨床に役立つ内容ですので、ぜひご覧ください。 講師 堀田一希先生 在宅リハビリテーション・ケアスクール登録講師 株式会社未来図Labo 理学療法士 理学療法士免許取得後、関西の整形外科リハビリテーションクリニックへ勤務し、その後介護分野でのリハビリテーションに興味を持ち、宮﨑県のデイサービスに転職。現在はデイサービスの管理者をしながら自治体との介護予防事業なども行っている。
介護施設におけるリハビリ職種の役割を考える
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
介護施設と言っても、特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院など、それぞれの施設で求められるリハビリ職種の役割は大きく異なります。 本動画では、各施設の特徴や利用者のニーズに応じたリハ職の関わり方を詳しく解説。 生活機能の維持・向上、チームケアの推進、利用者一人ひとりの「その人らしさ」を支える視点まで、現場で即実践できるヒントが満載です。 多職種連携のポイントや、現場での課題解決策にも踏み込みます。 講師 波野優貴先生 理学療法士 福祉用具プランナー管理指導者 シーティングコンサルタント 勤務先 ◯SOMPOケア株式会社 ◯大阪府立大学 非常勤講師 福祉用具論の一部を担当
X線画像から読み解く肩関節疾患
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
肩関節疾患は多様で複雑。 画像診断力を高めることは、適切な評価・治療方針の決定に直結し、リハビリテーションの質を大きく向上させます。 本動画では、肩関節疾患におけるX線画像の基本的な読み方から、臨床で遭遇する頻度の高い疾患の特徴的所見、診断のポイントまでを、わかりやすく解説。 実際の画像を用いて、明日からの臨床でリハビリテーションにすぐ活かせる知識と技術を身につけましょう。 理学療法士、作業療法士はもちろん、柔道整復師やトレーナー、医療従事者におすすめの内容です。 講師 井尻朋人先生 医療法人寿山会 法人リハビリテーション部 部長 理学療法士 保健学博士 認定理学療法士(運動器) 認定理学療法士(管理・運営) (公社)大阪府理学療法士会 理事 東大阪市理学療法士会 会長
忙しい現場でもできる!リハビリ部門スタッフのやる気を引き出す方法【42分】(550円/レンタル30日見放題)
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
スタッフのモチベーション向上で職場を活性化しませんか? リハビリ部門で働く皆さん、こんなお悩みはありませんか? 忙しすぎてスタッフのモチベーション管理まで手が回らない スタッフが仕事にやりがいを感じられず、モチベーションが下がっている チーム内の雰囲気が悪く、活気がない スタッフの評価やフィードバックが不足し、不満が生じている これらの問題を放置すると、離職率の上昇や職場の生産性低下につながる可能性があります。 しかし、ちょっとした工夫で、スタッフのやる気を引き出し、働きやすい職場環境を作ることができます。 今回のセミナーでは、 「忙しい現場でもできる!リハビリ部門スタッフのやる気を引き出す方法」 をお伝えします。 具体的な実践方法を学び、すぐに職場で活かせる内容となっています。 講師 高木綾一先生 株式会社Work Shift 代表取締役 国家資格キャリアコンサルタント リハビリテーション部門コンサルタント 医療・介護コンサルタント 理学療法士 認定理学療法士(管理・運営) 呼吸療法認定士 修士(学術)(経営管理修士) 関西医療大学保健医療学部 客員准教授
頚椎の機能解剖
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
超高齢化社会となり頚椎疾患を有する人も増えています。 また、デスクワークにより頚椎由来の症状が出る方も増えています。 頚椎は頭部と体幹部の中間に位置し、様々な神経や血管の通り道になっています。 そのため、頚椎の変性や損傷は疼痛の増悪、ADL低下、生命の危機につながる可能性があります。 リハビリ職種として頚椎由来の疾患の評価や治療を行うためには機能頚椎の解剖を理解することが重要です。 頚椎の機能解剖に無知な状態で頚椎の運動療法は非常にハイリスクとなります。 本動画では頚椎の機能解剖をイラストを用いてわかりやすく解説をしております。 講師 福山真樹先生 理学療法士 メディカルアナトミーイラストレーター リハビリテーション・ケアを描く臨床漫画家 医療関係専門イラストスタジオ福之画:代表 京都芸術大学 非常勤教員 美術解剖学
高齢者の円背姿勢に対するリハビリテーションの考え方と実践
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
高齢者のリハビリテーションにおいて悩むことの一つとして円背姿勢がある。 円背姿勢があると、立ち上がり、歩行などの基本動作や呼吸、嚥下にも問題が出来ることが多い。 本動画では高齢者の円背姿勢に焦点をあて、リハビリテーションの考え方や実践的な介入方法について解説をしております。 円背姿勢を解剖学・運動学の視点より解釈し、評価から治療介入までお話をいたします。 堀田一希先生 在宅リハビリテーション・ケアスクール登録講師 理学療法士
訪問リハビリにおける作業療法の在り方
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
作業療法士として訪問リハビリはどうあるべきか? このことに焦点を当てた動画となります。 訪問リハビリで作業療法を実践するためには、作業療法とは何か?という本質を理解することが重要です。 作業療法を訪問リハビリの中で提供することが出来れば、より利用者の自立と自律を促せる可能性高くなります。 訪問リハビリや在宅リハビリに関わる作業療法士に必見の内容となっています。 講師 浅田健吾先生 作業療法士 株式会社colors of life 訪問看護ステーション彩 在宅リハビリテーション&ケアスクール 講師
科学的根拠に基づく肩の整形外科徒手検査法
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
肩関節の整形外科徒手検査法について科学的根拠や臨床思考の観点より解説した動画となります。 整形外科徒手検査の意義 感度や特異度とは何か 肩関節疾患別の検査法について解説をしております。 また、肩関節整形外科徒手検査法の実際の方法を動画を用いて解説しておりますので大変理解しやすい内容になっております。 肩関節疾患のリハビリテーションに携わる職種にとって最適な動画となっております。 講師 竹中孝博先生 平成医療短期大学 准教授 作業療法士 博士(保健学)専門分野 運動器作業療法 神経生理学 慢性期片麻痺患者に対する運動イメージ介入
日常生活動作の改善に必要な上肢機能の基礎知識
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
リハビリテーションの臨床において、課題となるものとして上肢機能の改善があります。 脳血管疾患・運動器疾患では上肢機能が著しく低下する症例がいます。 上肢機能は日常生活に与える影響が大きく、QOLとの高い関連が指摘されています。 上肢機能の改善には体幹機能、姿勢制御、各関節の運動機能を包括的に評価する必要があります。 本動画では上肢機能の研究と臨床を専門としている久納健太先生より上肢機能の基礎知識についてわかりやすく解説をして頂いております。 明日からの臨床にお役に立てる内容となっています。 講師 久納健太先生 医療法人和光会山田病院 リハビリテーション部 作業療法士 修士(保健医療学) 関西医療大学大学院保健医療学研究科 博士後期課程在籍
変形性膝関節症の病態と評価
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
変形性膝関節症に対して漫然と可動域練習や筋力トレーニングをするのではなく、根拠のある評価と介入が必要です。 本動画では変形性膝関節症の病態や疼痛の機序を解説しております。 特に、リハビリテーションを行う上で必須の知識となる解剖学・運動学・病理学について詳細に学ぶことができます。 内容 1)変形性膝関節症の病態 2)変形性膝関節症に見られる特徴 3)変形性膝関節症における評価 講師 光田尚代先生 整形外科きょうたにクリニック 理学療法士 認定理学療法士(運動器) 介護支援専門員 メンタルヘルス・マネジメントⅡ種 ポジショニングセレクター1級 地域ケア会議推進リーダー 介護予防推進リーダー
足部の機能解剖
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
足部は大小28個の骨ででき、筋肉や靭帯が密集している部位となります。 そのため、足関節は多くの関節で構成されており、様々な方向に関節が動くことで足部機能が発揮されています。 足部を荷重・非荷重に分けて評価することで、足部機能の破綻を見極めることができますが、荷重・非荷重での足部の動きも異なってきます。 本動画では複雑な解剖学・運動学を有する足関節についてメディカルアナトミーイラストレーターの福山真樹先生にご解説をいただきます。 福山真樹先生 理学療法士 メディカルアナトミーイラストレーター リハビリテーション・ケアを描く臨床漫画家 医療関係専門イラストスタジオ福之画:代表 京都芸術大学 非常勤教員 美術解剖学
新人PT・OTでもわかる姿勢・動作分析のコツ
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
動作分析の評価があってこそ、的確な運動療法の実施が可能となります。 しかし、姿勢や基本動作の動作分析は簡単でありません。 正常動作を覚えることは必須ですが、正常動作を覚えるだけで臨床における動作分析ができる訳ではありません。 本動画では姿勢・動作分析を行う上でのコツについて高橋先生よりご解説を頂いております。 内容 1)評価での考え方と動作の実用性 2)現象を構成する関節運動 3)隣接関節の運動との関連 4)動作観察時に必要な環境設定 高橋優基先生 理学療法士 保健医療学修士 神戸リハビリテーション衛生専門学校
足関節不安定症の評価と治療
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
足関節不安定症とは、足首のぐらつきや疼痛のために 日常生活やスポーツの動作に大きな支障がでるものです。 多くの患者が過去の捻挫の治療が十分でなかった結果、足関節の靭帯が弛緩していることや加齢に伴う足関節の変形が原因で生じることがあります。 しかし、足関節不安定症の患者の対応は、装具や痛み止めの処方に終始することが多く、正しいリハビリテーションが提供されることが少ない状況です。 本動画では足のスペシャリストの山口剛司先生より、「足関節不安定症の評価と治療」について臨床的な視点よりご解説をいたします。 山口剛司先生 アルトリスト代表 理学療法士 運動器疾患、スポーツ選手の臨床が豊富で全国各地で足部・足関節の関節可動域、筋力、アライメントなどの関節機能や歩行などの動作分析を行い、個人に適したインソールを作成する足部・足関節のスペシャリスト
小児リハビリテーションに必要な精神発達遅滞の基礎知識
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
小児リハビリーテンションではしばしば精神発達地帯への対応が問題となります。 精神発達地帯は、知的機能の障害がおおむね18歳までにあらわれ、日常生活に支障が生じます。 何らかの特別な支援を必要とする状態となることが多い精神発達地帯ですが、精神発達地帯の特性をまず知ることが支援の第一歩となります。 本動画では ADHD(注意欠如・多動症) ASD(自閉スペクトラム症) LD(学習障害) の特徴ならびにリハビリーテンションにおける対応についてもご解説いたします。 講師 徳山義之先生 理学療法士 医療法人社団石鎚会 京都田辺中央病院 リハビリテーション部
2024年度診療報酬・介護報酬改定から考える訪問看護の運営・経営
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
本動画は2024年度診療報酬・介護報酬改定における訪問看護の内容についてポイントを整理して解説をしております。 2025年以降にも訪問看護を継続的に運営していくためには今回の同時改定の内容を把握し、今後の対策を検討するが非常に重要です 動画では訪問看護に求められるべき機能や今後の運営・経営についてもご解説を頂いております。
高齢者のための下肢の機能的トレーニング
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
加齢にともな身体活動の減少によりバランス機能や歩行能力が低下し、転倒・骨折が増加します。 転倒・骨折後は外出することが億劫となり、家に閉じこもりになることが増えます。 それにより、フレイル・サルコペニアが進行し、さらに歩行等が不安定になる悪循環が生じます。 バランス能力や歩行能力に大きな影響を与えるのが、下肢機能です。 本動画では高齢者の下肢機能の改善のためのトレーニングについて解説をしたものです。 講師 福山真樹先生 理学療法士 メディカルアナトミーイラストレーター リハビリテーション・ケアを描く臨床漫画家 医療関係専門イラストスタジオ福之画:代表
リハビリ職種が知っておきたい集団リハビリテーションの評価と実践のコツ
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
集団リハビリテーションの実践に難渋しているリハビリ職種は多いのではないでしょうか? 学生時代の実習では、個別リハビリテーションしか経験していないリハビリ職種が多く、集団リハビリテーションの評価、メリット、デメリットなどを学べていない状況かと思います。 本動画では、集団リハビリテーションとは何かという本質について解説を頂くとともに、実際の集団リハビリの評価や実践状況について解説をして頂きます。 講師 堀田一希先生 在宅リハビリテーション・ケアスクール登録講師 株式会社ハラケアシステム たでいけ至福の園 理学療法士
リハビリ職種が知っておきたい心臓リハビリテーションの基礎知識
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
高齢化の進展に伴い心不全患者が増大しております。 そのため、近年の診療報酬改定においても心臓リハビリテーションに着目した改定が行われており、リハビリ職種の心臓リハビリテーションの関りが期待されています。 心臓リハビリテーションは多面的かつ包括的な介入が必要となりますが、その実践のためには心臓に関連する基礎知識が最重要となります。 本動画ではリハビリ職種が心臓リハビリテーションに関与するための基礎知識や安全な運動療法を行うためのリスク管理に関する知識について解説をいたします。 講師 井上拓也先生 医療法人 白岩内科医院 理学療法士 高度専門士 3学会合同呼吸療法認定士 心臓リハビリテーション指導士 認定理学療法士(循環) サルコペニア・フレイル指導士
リハビリ職種が知っておきたい褥瘡予防の基礎知識
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
近年、重度者へのリハビリテーションに関わることが増えており、褥瘡予防への関りがリハビリ職種にも求められます。 本動画では褥瘡の発生要因、治癒過程、褥瘡予防について解説をしております。 「短絡的に体位交換だけをすればよい」という短絡的な考えではなく、エビデンスに基づく多様な介入が褥瘡予防には必要となります。 リハビリ職種が褥瘡に関わるためにも、褥瘡のメカニズム、他職種との連携、褥瘡ケアを理解しておくことが重要です。 講師 波野優貴先生 理学療法士 福祉用具プランナー管理指導者 シーティングコンサルタント 勤務先 ◯SOMPOケア株式会社 ◯大阪府立大学 非常勤講師
足底腱膜炎に対する評価と治療
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
足底腱膜炎はオーバーユースの1つであり、歩行、ランニング・ジャンプ動作が量的に過剰になった場合に発生すると言われています。 一方で、足部機能の低下や足部アライメントの異常によっても発症すると報告されています。 したがって、足底腱膜炎の治療では足底への負荷の量とアライメントコントロールの両方が必要と言えるでしょう。 本動画では足底腱膜炎の病態・発生機序・評価・治療について足部のスペシャリストである山口剛司先生よりご解説をいただきます。 講師 山口剛司先生 アルトリスト代表 理学療法士 mysole協会最高技術顧問 運動器疾患、スポーツ選手の臨床が豊富で全国各地で足部・足関節の関節可動域、筋力、アライメントなどの関節機能や歩行などの動作分析を行い、個人に適したインソールを作成する足部・足関節のスペシャリスト
セラピストが知っておきたい痙縮に対する物理療法の評価と介入
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
脳卒中の臨床に関わるセラピストにとって痙縮へのアプローチはぜひ習得しておきたいものです。 そこで、脳卒中後の機能障害である痙縮に対する物理療法、特に振動刺激を用いたアプローチを解説します。 痙縮の基礎から振動刺激の作用までわかりやすく解説いたします 振動刺激の作用機序から効果的な効果判定方法を分かりやすくご紹介いたします。 講師 久納健太 医療法人和光会山田病院 リハビリテーション部 作業療法士 修士(保健医療学) 関西医療大学 準研究員
透析患者に対するリハビリテーション~リスク管理と介入について~
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
透析患者は、様々な合併症(高血圧・貧血・循環不全・低栄養等)を有しており、急変のリスクは高いと言えます。 そのため、リハビリテーションを実施が難しいと感じている方も多いのではないでしょうか? 本動画では、透析患者へのリハビリテーションに関わる理学療法士が透析患者に対するリスク管理や具体的な介入などについて解説いたします。 腎臓リハビリテーションにご興味がある方にとっても有意義な動画となっております。 講師 井上拓也先生 医療法人 白岩内科医院 理学療法士 高度専門士 3学会合同呼吸療法認定士 心臓リハビリテーション指導士 認定理学療法士(循環) サルコペニア・フレイル指導士
リハビリテーション職種が知っておきたい転倒リスク評価の基礎知識
- ¥ 550 / レンタル ( 30 日 )
病院内や高齢者施設では、転倒・転落事故は、ほぼ日常的に発生する危機事象です。 理学療法士、作業療法士は安全管理の視点より、転倒予防に関わる機会が増えています。 転倒予防の第一歩は転倒リスクを評価し、リスクに応じて適切な対応を講じることです。 転倒リスク評価を用いれば定期的なスクリーニング評価やスタッフの転倒に対する教育も活用することができます。 本動画では、転倒リスクの評価の基礎知識についてわかりやすく解説をしています。 講師 堀田一希先生 在宅リハビリテーション・ケアスクール登録講師 株式会社ハラケアシステム たでいけ至福の園 理学療法士
ショップ管理者にチップを送って応援しよう!
チップを送る